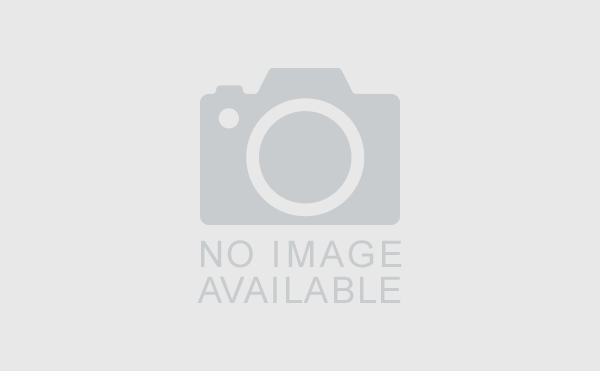車検代の勘定科目と仕訳を税理士が解説|修繕費?車両費?正しい処理方法とは

事業で車を所有していると、必ず数年に一度やってくるのが「車検」です。車検代は決して安い金額ではなく、勘定科目をどうするか迷う経営者の方も多いのではないでしょうか。修繕費なのか、車両費なのか、あるいは保険料や租税公課も含まれるため、一括処理してしまうと会計上も税務上も誤解が生じかねません。この記事では、税理士としての実務経験を踏まえ、車検代の勘定科目と仕訳の考え方をわかりやすく解説します。
車検代の勘定科目はどう考える?
車検代には複数の性質が含まれており、「まとめて処理」するのは適切ではありません。主に以下の項目に分かれます。
- 修繕費(点検整備費用)
オイル交換・ブレーキパッド交換など、通常の維持管理として発生する費用は「修繕費」で処理するのが一般的です。 - 車両費(整備費用を含む場合)
会社によっては、上記の修繕費など車に関する費用をまとめて「車両費」として処理するケースもあります。実務上、仕訳をシンプルにする目的で採用されることもあります。 - 保険料(自賠責保険)
車検時に支払う自賠責保険料は「保険料」として処理します。勘定科目をまとめてしまうと後から分析できなくなるため、分けておくのがおすすめです。 - 租税公課(重量税・印紙代など)
法定費用にあたる部分は「租税公課」で処理します。大阪市内の顧問先でも、この部分を「車両費」に含めてしまっていたケースを見かけましたが、後から確認しづらくなるため注意が必要です。 - 支払手数料(車検代行費用など)
ディーラーや代行業者に依頼した場合の「代行手数料」は「支払手数料」で処理するのが適切です。この部分を他の科目に混ぜると、費用の性質が不明確になります。
👉 ポイントは、「車検代は一式で処理せず、内訳を分解して勘定科目ごとに仕訳する」ことです。これにより決算資料も見やすくなり、税務調査の際も説明がしやすくなります。
車検代の具体的な仕訳例
例:車検代の総額 130,000円
(内訳:整備費 60,000円、自賠責保険 25,000円、重量税 30,000円、印紙代 5,000円、代行手数料 10,000円)を普通預金から振込で支払った場合
| 借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 車両費 | 60,000 | 普通預金 | 130,000 |
| 保険料 | 25,000 | ||
| 租税公課 | 35,000 | ||
| 支払手数料 | 10,000 |
実務上は、会計ソフトの摘要欄に「車検代(整備費〇円・自賠責〇円・重量税〇円・代行手数料〇円)」と入力しておくと、後から確認する際に非常に便利です。特に税務署から確認を求められたときに、領収書と仕訳がすぐに対応できると安心です。
実務での注意点とよくある失敗例
1. 車検代を全額「修繕費」で処理してしまう
実務で非常に多いケースです。確かに処理は簡単ですが、租税公課や保険料、支払手数料まで含めてしまうと、勘定科目の意味が曖昧になります。
2. 消費税の取り扱い
車検代の中には、消費税のかかる整備費用や部品代のほかに、自動車重量税(不課税)や自賠責保険料(非課税)といった、消費税の対象外となる費用も含まれています。そのため、車検代をまとめて処理するのではなく、内容を分けて仕訳することが大切です。
3. 資金繰りへの影響
車検代は数年に一度まとまった金額が出ていきます。特に複数台を所有している会社では、同じ時期に集中することもあり、資金繰りに影響することがあります。予算に組み込んでおくのが実務的な工夫です。
まとめ
車検代は「車両費」「保険料」「租税公課」「支払手数料」など複数の性質を持つ費用の集合体です。単純に「修繕費」として処理するのではなく、内訳を分けて仕訳することが正しい会計処理につながります。実務でも処理方法に迷うケースは多く、特に消費税の課税・不課税・非課税の区分を意識することが重要です。当事務所(大阪市)でも、車検代や車両関連費用の処理に関するご相談を数多くいただいています。車検代の仕訳で迷った際には、ぜひお気軽にご相談ください。

著者紹介
「小さな会社と個人事業主の専門税理士」、吉川拓税理士事務所の吉川です。
10年以上にわたり、小規模事業者や個人事業主の皆さまを税理士としてサポートしてきました。
現在は大阪市で開業していますが、オンライン対応により地方や離島を含め全国対応しております。
会計や税金が苦手な方にも、専門用語を使わず分かりやすく、親身に寄り添うことを心がけています。
趣味はトイプードル、コーヒー、読書。お気軽にご相談ください。