印紙代の勘定科目と仕訳|経理初心者が迷いやすいポイントを税理士が解説
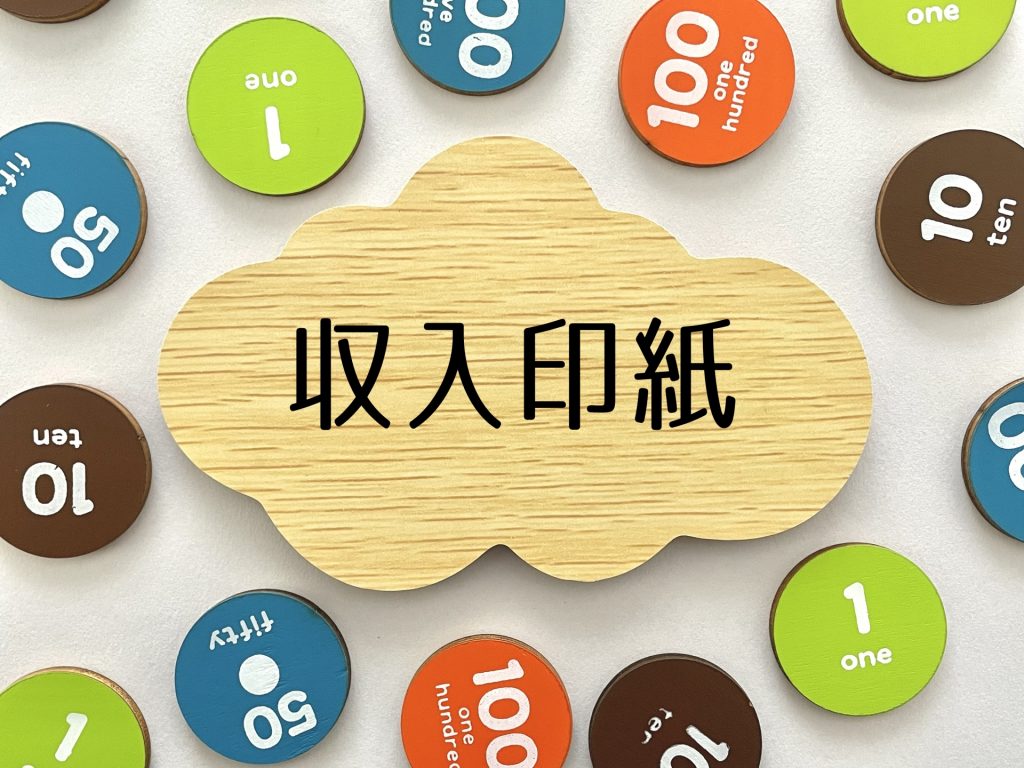
契約書や領収書に貼る収入印紙は、日常的な取引では金額が小さくても、積み重なれば無視できないコストになります。特に勘定科目の選び方や仕訳処理は、経理初心者が迷いやすい部分です。本記事では印紙代に関する基本的な考え方から、実務の現場でよくある注意点までを税理士の視点で解説します。
目次
印紙代に使われる代表的な勘定科目
印紙代は一見単純な支出ですが、勘定科目の選び方で迷うことが多い費用のひとつです。代表的な処理方法は次のとおりです。
1. 租税公課
もっとも一般的な勘定科目は「租税公課」です。印紙税は税金の一種であり、契約書や領収書に課される法定費用です。そのため、多くの会社では「租税公課」で処理するのが基本となります。
仕訳例
| 借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
2. 貯蔵品(購入時に資産計上する方法)
まとめて印紙を購入してストックしておく場合には「貯蔵品」として資産計上するケースもあります。
たとえば1万円分の印紙を一度に購入した場合、その時点では「貯蔵品」として計上し、実際に契約書等に貼付した時点で「租税公課」に振り替えます。
仕訳例(購入時)
| 借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 貯蔵品 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
仕訳例(使用時)
| 借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 1,000 | 貯蔵品 | 1,000 |
実務での確認ポイント
👉 実務的には印紙の購入額が少額なら購入時にそのまま「租税公課」で処理して差し支えありません。ただし、まとまった額を購入する企業では「貯蔵品」で管理した方が、残高管理がしやすくなります。
3. 決算で貯蔵品に振り替える方法
もうひとつ実務でよく行われるのが「購入時は租税公課で処理し、決算時に未使用分を貯蔵品へ振り替える方法」です。日々の経理処理をシンプルにできるメリットがあります。
仕訳例(購入時・通常処理)
| 借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
仕訳例(決算時・未使用分が3,000円残っていた場合)
| 借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 貯蔵品 | 3,000 | 租税公課 | 3,000 |
実務での確認ポイント
👉 この処理方法なら普段の仕訳は簡単になり、年に一度の決算で残高調整を行うだけで済みます。経理担当者が少ない中小企業や、印紙を頻繁に購入しない会社ではこのやり方も現実的です。
※郵便局で購入するものといえば、収入印紙以外にもレターパックがあります。こちらも「どの勘定科目で処理すればよいか」と迷うことが多い費用です。
詳しくは 下記のレターパックの仕訳と勘定科目をご覧ください。
印紙代の仕訳で注意すべき実務上のポイント
税理士事務所での実務経験から、印紙代の処理でよく見かける注意点をまとめます。
- 消費税区分を間違えない
印紙税は原則として「非課税取引」にあたるため、仕訳時に課税区分を誤らないことが重要です。 - 領収書への印紙の貼り忘れ
印紙税が課される領収書では、貼り忘れだけでなく、貼った印紙に消印がされていない場合も注意が必要です。消印がないと、税務調査で過怠税を課されるリスクがあります。日常的に確認する習慣を持つことが大切です。 - 実務の事例
ある顧問先では、すべて「租税公課」で処理していた結果、決算時に大量の未使用印紙が残っていることが判明。そこで「決算時に貯蔵品に振り替える方式」に変更し、経理の整合性と実態が合うように改善ができました。
税理士の視点から見た印紙代処理の考え方
- 処理方法の統一が大切
購入時から「貯蔵品」にするか、決算でまとめて振り替えるか、いずれにしても会社としてのルールを決め、処理を統一することが重要です。 - 経営への影響を意識する
印紙代は少額でも、契約が多い業種では年間で大きなコストになります。管理を怠ると資金繰りの見通しにも影響します。 - 税務調査でのチェックポイント
科目処理が一貫していないと調査で指摘されやすくなります。日常の処理から決算までの流れを整理しておくことが、安心につながります。
まとめ
印紙代は小さな経費に見えますが、処理方法によっては決算や税務調査に影響します。代表的な方法は次の3つです。
- 租税公課で処理(最も一般的)
- 貯蔵品で処理し、使用時に租税公課へ振替
- 租税公課で処理し、決算で未使用分を貯蔵品へ振替
自社に合ったルールを選び、処理を統一することがポイントです。
印紙代のような「少額だけど積み重なる経費」こそ、正しい仕訳ルールが資金繰りや税務の安心感につながります。実際に、当事務所の顧問先でも「少額だから後回しにしていた」というご相談をいただくことがあります。そんな小さな疑問も一緒に解決していくのが、私たちの役割だと考えています。大阪で経理にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

著者紹介
「小さな会社と個人事業主の専門税理士」、吉川拓税理士事務所の吉川です。
10年以上にわたり、小規模事業者や個人事業主の皆さまを税理士としてサポートしてきました。
現在は大阪市で開業していますが、オンライン対応により地方や離島を含め全国対応しております。
会計や税金が苦手な方にも、専門用語を使わず分かりやすく、親身に寄り添うことを心がけています。
趣味はトイプードル、コーヒー、読書。お気軽にご相談ください。



