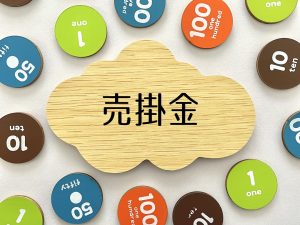コピー代(プリント代)の勘定科目と仕訳|経理初心者が迷いやすいポイントを会計のプロが解説

コピー代は日常的に発生する小さな経費ですが、勘定科目の選び方や仕訳方法に迷う方が少なくありません。特に個人事業主や小規模法人では「通信費?消耗品費?雑費?」と悩むケースが多く、実務でもよく質問を受けます。本記事ではコピー代の勘定科目と仕訳の考え方を、税理士事務所ならではの視点からわかりやすく解説します。
目次
コピー代に使われる代表的な勘定科目
コピー代は一律で「この科目」と決まっているわけではなく、利用目的や会計方針によって使い分けられます。代表的な科目は以下のとおりです。
- 消耗品費:文房具やコピー用紙など、少額で使用期間が1年未満の物品を購入した際に使う科目。コンビニでのコピーや、社内プリンターでの出力にかかる紙・インク代をまとめて処理する場合、消耗品費を使うことが多いです。
- 通信費:電話代・切手代など、情報伝達や通信に関連する支出に使う科目。取引先にFAX送信をするためにコンビニでコピー兼FAXを使った場合などは通信費に含めて処理することもあります。
- 雑費:どの科目にも分類しにくい少額の支出を処理するための科目。仕訳を細かく切り分けるのが非効率な場合、「雑費」にまとめることも可能です。ただし雑費は使いすぎると「何に使ったか分からない経費」が多くなってしまうので注意が必要です。会計事務所としては「どうしても他の勘定科目で仕訳できない支出だけ雑費で」というのが基本スタンスとなります。
まとめると
- 基本は「消耗品費」で処理するのが無難。
- 通信としての性質が強い場合は「通信費」。
- 他の科目で処理できない場合はやむを得ず「雑費」。
実務での確認ポイント
実務的には「消耗品費」とするケースが多いですが、会計方針として統一しておくことが大切です。顧問先でも、同じ「コピー代」なのに担当者ごとに違う科目を使ってしまい、毎月の経費集計がバラつく例を何度も見てきました。
コピー代の仕訳例
では実際に仕訳でどう表すのか、具体例を紹介します。
例:コンビニでコピー代500円を現金で支払った場合
| 借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 500 | 現金 | 500 |
例:会社で業務資料をコピーし、後日請求書で支払う場合
| 借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 3,000 | 未払金 | 3,000 |
例:FAX送信サービスを利用し、現金で支払った場合
| 借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 通信費 | 200 | 現金 | 200 |
実務での確認ポイント
このように、目的と支払方法に応じて仕訳を整理することが重要です。実際の現場では、少額だからとレシートをまとめて「雑費」で処理してしまうこともありますが、後から見返した時に「何に使ったのか」が不明になりやすく、税務調査で質問を受けるリスクもあります。
コピー代処理の注意点と現場感覚
実務上よくある注意点を、実際の事例を交えてご紹介します。
① 入力担当者による科目のバラつき
ある顧問先では、同じコンビニコピー代を「消耗品費」と処理する人もいれば「雑費」と処理する人もいて、月次試算表が乱れていました。最終的には「コピー代は消耗品費に統一」とルール化することで解決。勘定科目をそろえるだけで決算書の見やすさが大きく変わります。
② コピー機リース料と混同するケース
コピー代とコピー機のリース料は別物です。コピー代は都度発生する経費ですが、リース料は「リース料」等で処理する必要があります。ある会社ではすべて「消耗品費」で処理してしまい、経費の内訳が不自然になっていました。税務署からも「リース契約なのか都度利用なのか」を確認されやすい部分です。
③ 少額経費でも積み重なると大きな金額に
コピー代は1回数百円ですが、月に何十回も利用すれば数千円~数万円に膨らみます。特に営業職が多い会社や、申請書類を大量に扱う時期(たとえば確定申告や補助金申請のピーク)には意外と大きな金額になります。「少額だからと適当に処理しない」という意識が必要です。
まとめ
コピー代の仕訳は少額ながらも積み重なると大きな金額になり、決算や資金繰りに影響することもあります。実際に、当事務所の顧問先でも『領収書が整理できていない』『雑費にしてしまった』というご相談をよくいただきます。大阪で事業をされている方で同じようなお悩みがあれば、当事務所が実務に即したサポートをご提供できますので、安心してご相談ください。

著者紹介
「小さな会社と個人事業主の専門税理士」、吉川拓税理士事務所の吉川です。
10年以上にわたり、小規模事業者や個人事業主の皆さまを税理士としてサポートしてきました。
現在は大阪市で開業していますが、オンライン対応により地方や離島を含め全国対応しております。
会計や税金が苦手な方にも、専門用語を使わず分かりやすく、親身に寄り添うことを心がけています。
趣味はトイプードル、コーヒー、読書。お気軽にご相談ください。