売掛金の仕訳をやさしく解説|会計のプロが現場感覚で伝える実務ポイント
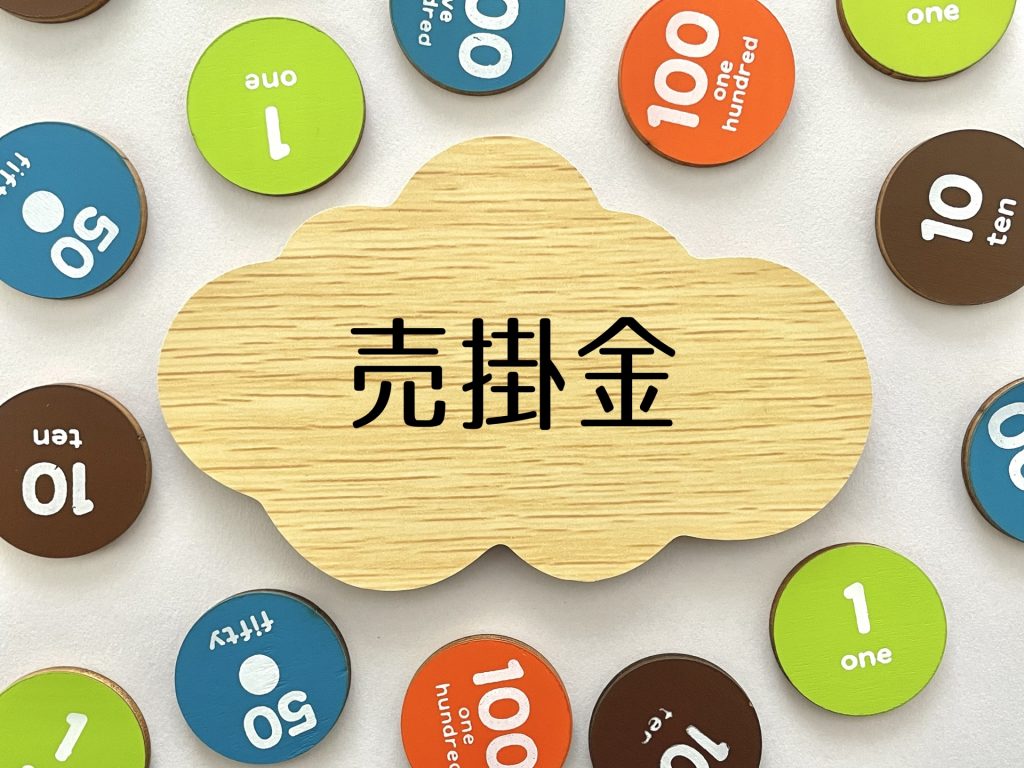
「売掛金の処理は難しい」と感じる方は少なくありません。特に中小企業や個人事業主では、現金取引と違い、売掛処理は慣れるまで戸惑いやすいポイントです。今回は、税理士事務所の実務経験を交えながら、売掛金仕訳の基本から現場での注意点まで解説します。
売掛金の基本と仕訳の流れ
売掛金とは、商品やサービスを提供したものの、まだ代金を受け取っていない状態のことを指します。会計上は「資産」として扱われ、将来現金化される権利という位置づけになります。
仕訳の基本例
- 商品を掛けで売価110,000円で販売した場合(税込経理の場合)
| 借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 110,000 | 売上 | 110,000 |
- 後日、普通預金に入金があった場合
| 借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 110,000 | 売掛金 | 110,000 |
このように、「発生時」と「回収時」に分けて仕訳するのがポイントです。
現場での注意点
実務の現場では、特に中小企業で「売上を立てるのは入金日」と考えてしまうケースがよくあります。しかし税務上は、商品を引き渡した日やサービスを提供した日が売上日となり、その時点で売掛金を計上する必要があります。
当事務所で新たにご相談に来られたある会社でも、「入金ベース」で処理していたため、税務調査で売上計上漏れを指摘され、修正申告となった事例がありました。売掛金の仕訳は、単なる会計処理ではなく、税務調査対策の観点からも重要です。
実務でよくある売掛金の処理ミスと注意点
売掛金の仕訳において、現場でよく見かけるミスはいくつかあります。
① 入金手数料を処理していない
銀行振込の場合、振込手数料を差し引かれて入金されることがあります。
例えば、請求額110,000円に対して、実際の入金が109,670円だった場合:
| 借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 109,670 | 売掛金 | 110,000 |
| 支払手数料 | 330 |
この仕訳を正しく行わないと、売掛金残高が合わなくなり、後で帳簿と実際残高がズレる原因になります。
② 売掛金残高の回収漏れ
売掛金が残ったまま放置されているケースも少なくありません。特に年末や決算前に「売掛金が回収されていない」と慌てる会社を数多く見てきました。顧客管理が甘いと貸倒リスクに直結するため、月次で残高をチェックする仕組みが必要です。
実務での確認ポイント
あるIT系の顧問先で、月末に入金消込を行った際、数件の売掛金が帳簿と合わないことが判明しました。調べてみると、振込手数料を売掛金の仕訳に反映していなかったことが原因でした。この見落としが積み重なると、決算で「現金残高と売掛金残高が合わない」という大きなトラブルにつながります。以後、この会社では「請求書と仕訳を突き合わせる」というフローを必ず行うよう改善しました。
入金消込・滞留売掛金への対応と現場の工夫
売掛金管理の最も大切なポイントは「入金消込」です。帳簿上の売掛金と実際の入金を毎月照合し、残高が正しいかを確認します。クラウド会計ソフトを利用している場合でも、自動仕訳に頼りすぎず、必ず請求書と突き合わせることが大切です。
実務での工夫例
- 月末ごとに「売掛金残高一覧表」を出力してチェックする
- 振込予定日をエクセルやクラウドで共有し、営業担当と経理担当で情報を一致させる
- 入金予定日を過ぎたものは、営業担当が取引先に確認するフローを設ける
締日と支払日は取引慣習として「月末締め・翌月末払い」が一般的です。このスケジュール感を理解していないと、売掛金の消込がずれ込み、現金繰りにも悪影響を与えることがあります。
顧問先での体験談
ある顧問先の社長から「月末に売掛金の残高が予想より多くて、帳簿と合わない」と相談を受けました。調べてみると、一部の入金が未確認で、実際には回収済みだったことが判明。小さな確認漏れが資金繰りの不安につながることを、改めて実感しました。売掛金は単なる帳簿上の数字ではなく、経営判断や現金管理に直結する重要な情報となるため必ず残高のチェックが必要です。
まとめ
売掛金の会計処理は、単純に見えて奥が深い分野です。基本は「発生時に売掛金を計上し、入金時に消込する」ことですが、実務では手数料処理や入金消込など細かい注意点が多く存在します。正しい仕訳と残高管理を徹底することで、税務調査対策だけでなく資金繰りの安定にもつながります。

著者紹介
「小さな会社と個人事業主の専門税理士」、吉川拓税理士事務所の吉川です。
10年以上にわたり、小規模事業者や個人事業主の皆さまを税理士としてサポートしてきました。
現在は大阪市で開業していますが、オンライン対応により地方や離島を含め全国対応しております。
会計や税金が苦手な方にも、専門用語を使わず分かりやすく、親身に寄り添うことを心がけています。
趣味はトイプードル、コーヒー、読書。お気軽にご相談ください。



