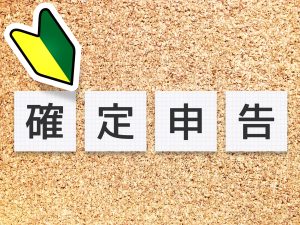消費税の原則課税と簡易課税とは?
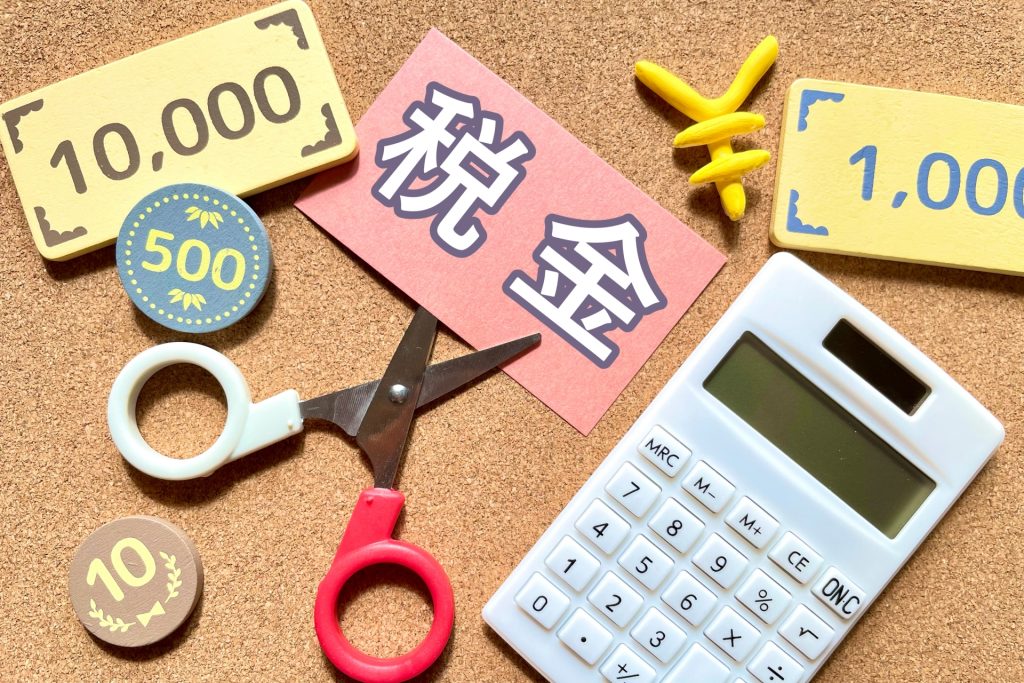
消費税の控除対象仕入税額の計算には原則的な方法(原則課税制度)と簡易な計算方法(簡易課税制度)があります。この2つを正しく理解して節税に繋げましょう。
消費税の計算方法は?
消費税は「預かった消費税」から「支払った消費税額」を控除して納付税額を計算する多段階累積控除という方法が採られています。
「預かった消費税額」−「支払った消費税額」=納付税額
この支払った消費税額を控除することを「仕入税額控除」といい、控除できる消費税額のことを「控除対象仕入税額」といいます。
消費税法ではこの控除対象仕入税額を計算する方法として原則課税(本則課税)制度と簡易課税制度の2つの方法が認められています。
原則課税制度とは?
原則課税制度を採用した場合、売上を「課税売上」と「非課税売上」に分類し、仕入を「課税売上に対応するもの」、「非課税売上に対応するもの」、「共通して対応するもの」にそれぞれ区分して計算します。
さらにこれらを区分したあと「個別対応方式」や「一括比例配分方式」という方法により控除対象仕入税額を計算していく必要があるため非常に手間がかかります。
簡易課税制度とは?
簡易課税制度は「預かった消費税額」に事業区分ごとに定められている「みなし仕入率」を乗じて控除対象仕入税額を計算する方法です。
このため「一括比例配分方式」のように売上や仕入を細かく分類する必要がなく、簡易な計算方法となります。
簡易課税制度の注意点!
① 届出書の提出
簡易課税制度を選択する場合は「消費税簡易課税制度選択届出書」を前課税期間の末日までに提出しなければなりません。
② 前々年の課税売上高5,000万円以下
簡易課税制度は基準期間における課税売上高が5,000万円以下の場合に適用できます。
このため基準期間における課税売上高が5,000万円を超えている場合は、たとえ簡易課税選択届出書を提出していたとしても原則課税で計算することとなります。
③ 2年間の継続適用
簡易課税制度を選択した場合は、2年間は継続して適用しなければならないため2年以内は原則課税に戻すことができません。
このため簡易課税制度を選択する場合は1年間の納税額ではなく2年間トータルで有利になるか判断する必要があります。
原則と簡易どっちが有利?
原則課税が有利な場合は、例えば大掛かりな設備投資を予定しているときなど「支払った消費税額」が大きくなる場合です。
一方簡易課税が有利な場合は、実際の「支払った消費税額」よりも「みなし仕入率」で計算した控除対象仕入税額のほうが大きくなる場合です。
実際には「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期限までに原則課税と簡易課税どちらが有利になるかをシミュレーションし選択する必要があります。
「消費税簡易課税制度選択届出書」は前課税期間の末日までに提出しなければならないため、今後2年間の設備投資予定や納税額を概算でシミュレーションし慎重に判断しなければなりません。
まとめ
今回は消費税の原則課税制度と簡易課税制度について説明しました。
簡易課税を選択した場合は原則課税に比べ手間がかからない点がメリットですが、2年間は継続適用しなければならない点に特に注意して選択するようにしましょう。

著者紹介
「小さな会社と個人事業主の専門税理士」、吉川拓税理士事務所の吉川です。
10年以上にわたり、小規模事業者や個人事業主の皆さまを税理士としてサポートしてきました。
現在は大阪市で開業していますが、オンライン対応により地方や離島を含め全国対応しております。
会計や税金が苦手な方にも、専門用語を使わず分かりやすく、親身に寄り添うことを心がけています。
趣味はトイプードル、コーヒー、読書。お気軽にご相談ください。